●あけましておめでとうございます
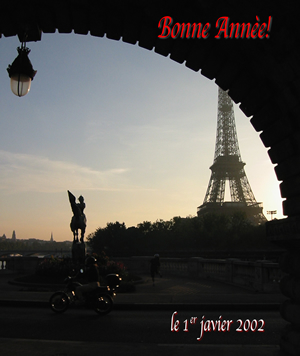 美味しいお酒を飲んでいる間に寝てしまい、年越しを夢の中でしてしまった。どんな夢を見たのかも忘れてしまった。悪夢ではなかったことだけは確かだけど。
美味しいお酒を飲んでいる間に寝てしまい、年越しを夢の中でしてしまった。どんな夢を見たのかも忘れてしまった。悪夢ではなかったことだけは確かだけど。
つねづね子どもたちに話しているのだが、幸せとか自由とか実に相対的なもので、今の自分のありようをどう受けとめるか、そこにすべての鍵が隠されているような気がしてならない。
個人的に言えば21世紀最初の1年は良い年だった。けっして楽観できない社会情勢の中でのほほんと暮らしてしまったという後ろめたさを感じるほど。時代の大きなうねりを感じとれる、もっと鋭敏な感覚を磨かなくてはいけないと感じている。正義の仮面をかぶった不正に立ち向かう力が欲しいと思う。少なくとも何が正しくて何が誤っているのか見きわめる力が欲しいと思う。
夢の中でうつらうつらしていてはだめだ、とアルコールの抜けない頭で思う。
●夏が来る前に
あまりに長いことご無沙汰をしてしまった人と顔を合わせるのが気詰まりで、余計に会えなくなってしまうということがよくある私は自分の周囲から友達を含めた数多くの知己を自分のせいで遠ざけてきてしまったと悔いることが何度もあった。過去の記録を上手に整理できない、大事な領収書や書類でさえも平気で散逸してしまう、そういうところのある私だから、絶えず変化しつづける生身の人間との連絡など明日になれば忘れてしまう。
新年の挨拶を書いてから3ヶ月、一度も気にならなかったわけではないのだが、自分の周りで動いている状況を書き留めるゆとりもなく、あるいはどう書き留めていいか考えている間に時間ばかりが過ぎていった。桜がいつになく早く咲いてしまったという、この星の異常な変化がまったく原因していないともいいきれないのだが、私の脳の中もこれまでどおりのリズムを失い、浮き足だった生活の中で、四囲の状況を的確につかみきれない状態だった。
人生を12年ごとに分けてその区切りをつけていくという中国のしきたりに何ら興味はないけれど、とにかくその陰陽学によれば4度目の区切りの歳を迎え、自分がこれまで生きてきた道のりを眺めていると、これから生きていく時間に大きな変貌もなく、全てが読めてしまいそうな予感におののくことがあり、自分という中心点から発する半径は360度無限に引けるはずなのにすでにその線の引ける角度はほとんど限定されてしまっている、と考えるのはとても恐いことで、かりにそれが安定した方向であったとしても柔らかな鉛筆でそっと引かれてしまった図面の上をなぞるだけの人生ならなんてつまらないんだろうと思う。選択不可のグレーのゾーンばかりが広がったメニュー表示を眺めながらため息をつく、リセットして新規作成したくとも人生ばかりはそうはいかない、しかし、無駄を承知の上で、その悲しみを粉砕するための悪あがきを今後の人生ではしていこうと思っている。

●ALT1249
森の中に土地を買った。標高1249mの傾斜地で、2月下旬、残雪のため私の車はその土地までたどり着けず、途中から歩いて山を登った。夏になればこんもりと緑が茂るはずだが、冬枯れの山は森というより雑木林の様相を呈していた。鹿の糞があちこちに落ちており、何頭かの鹿の足跡も雪の上に残っており、南側の山道を越えてその先の林の中に続いている。開発の手がどんどんとこの山麓を埋め尽くし、自然は変化している。私はその自然に対する侵略者に違いなく、実に複雑な思いなのだが、何とか自然と共存していきたいと思っている。
「ののの山荘」と名づけた山小屋はソローのように自分で建てることもできず、たくさんの負債を背負い込んで業者に建ててもらいはじめた。『森の生活』とは正反対の行き方だがこれが現実。カラ松に囲まれた山の生活が始まるのは夏休みに入ってから。自然が自分を受け入れてくれるかどうか、受験生のような気持ちで今から緊張している。
●Where I lived, and what I lived for
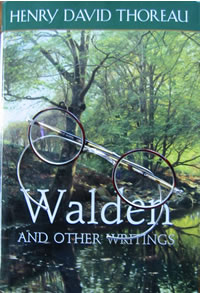 'I
went to the woods because I wished to live deliberately, to front only
the essential facts of life, and see if I could not learn what it had
to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.
I did not wish to live what was not life, living is so dear'
'I
went to the woods because I wished to live deliberately, to front only
the essential facts of life, and see if I could not learn what it had
to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.
I did not wish to live what was not life, living is so dear'
「私が森へ行ったのは思慮深く生き、人生の本質的な事実のみに直面し、人生が教えてくれるものを自分が学び取れるかどうか確かめてみたかったからであり、死ぬときになって自分が生きていなかったことを発見するようなはめにおちいりたくなかったからである。人生とはいえないような人生は生きたくなかった。生きるということはそんなにも大切なものだから」
48回目の誕生日を迎えた私は、ソローほどの決意はないものの、人間らしく生きるために、自分らしく生きるために残りの人生を見つめていきたい、と思う。
●選択肢
 山小屋の出来具合を見に出かけた。いまひとつはっきりしない天気だったが考えてみればここに居を構えるということは雨の日も風の日も嵐の日もここにそれなりの生活があるということで、お天気を見はからって出かけるペンションとは違うわけで、どんな天候でも気にせずに出かけることができる反面、天気を気にしていたら生活できないということなのだとあらためて思った。
山小屋の出来具合を見に出かけた。いまひとつはっきりしない天気だったが考えてみればここに居を構えるということは雨の日も風の日も嵐の日もここにそれなりの生活があるということで、お天気を見はからって出かけるペンションとは違うわけで、どんな天候でも気にせずに出かけることができる反面、天気を気にしていたら生活できないということなのだとあらためて思った。
霧のなかに姿はよくないけれど味わいのある山栗の木が生えている。他にもう一本大きな根元から二股に別れた大きな山栗があるが、この二本の山栗がののの山荘の Main Trees だ。三本あった山桜は建物を建てる位置の関係ですべて伐らざるをえなかった。りょうぶの木も貧弱なのが二本残っただけだった。木をとるか、仮の庵をとるか、わずかに悩んだけれどけっきょくわがままを通して倒してしまった樹木たちへの供養をどういうかたちでしていくかこれからの課題だ。
●器量・不器量
 ランニングをやめてから半年以上、代わりの運動もしていないから体は鈍りきっている。駅近くの公営駐車場に車を置いてFERMATAと二人山小屋の建築現場まで歩いた。わずかに起伏のあるアスファルト道を20分、そこから単線の踏切を渡り山道に入る。車の上れる急傾斜の砂利道は歩きにくい。鈍った腰の辺りに違和感を感じる。
ランニングをやめてから半年以上、代わりの運動もしていないから体は鈍りきっている。駅近くの公営駐車場に車を置いてFERMATAと二人山小屋の建築現場まで歩いた。わずかに起伏のあるアスファルト道を20分、そこから単線の踏切を渡り山道に入る。車の上れる急傾斜の砂利道は歩きにくい。鈍った腰の辺りに違和感を感じる。
ふと森の中に入っていく小径を見つけ入っていくとそこは同じ山の中でも別世界が広がる。落ちた松ぼっくりが地面に根を下ろし葉を出し始めている。たらの芽が摘みとられずにそのまま無精ひげのように伸びている。植林されたカラ松は並び方でそれとわかるのだが実生から自然に育った樹木は先輩植物たちの創り出した環境に自分を合わせてしぶとく生きている。森林公園、樹林公園などと名づけられた都会の「森」の木々はみな器量よしで、フィットネスクラブで鍛え上げられたスポーツマンのようだと不器量な山の自然児たちを見て思う。つつましく淡い朱色の山つつじは薄紅色のほっぺたをした田舎娘のようだ。
「工事に入ってからここで3回鹿を見たよ。親子づれの…」
大工の棟梁がいった。 刻んだ木の香りが辺りに漂った。
●持続する意志
 澤本和雄さんが走って日本一周をしたのはもう3年も前のことになる。難病に苦しむ人々にエールを送り、同時にその人たちへの福祉の充実を行政に訴えて6000Kを走った。当時はまだ私も元気で(今も元気だけど)、6000Kの一部をご一緒させてもらった。
澤本和雄さんが走って日本一周をしたのはもう3年も前のことになる。難病に苦しむ人々にエールを送り、同時にその人たちへの福祉の充実を行政に訴えて6000Kを走った。当時はまだ私も元気で(今も元気だけど)、6000Kの一部をご一緒させてもらった。
ウルトラマラソンのエキスパートを自負するある人はこの澤本さんの日本一周をまったく評価しようとしなかった。十全の準備と万全のサポートを得て、一日平均60K程度を走り続けるのは難しいことではないと公の場で言い放った。ま、そんな手合いのご託はどうだっていい。当の澤本さんの耳に入ってはいないだろうし、仮に入ったとしてもそういうことを気にする方ではないから。
その澤本さんがこの「がんばれ難病患者日本一周激励マラソン」の全記録を本に書かれた(『ゆっくりでいいんだよ』大巧社)。日記のすべては手書きで、走りながら出会った植物や昆虫などの絵もすべて澤本さんが描かれた。それはあたたかさにあふれた本である。たった2000部だが、たぶんあまり売れないだろう。たくさんの人たちにぜひ読んでもらいたい本が売れない時代である。
一日も休むことなく、つねに同じペースで走り続けること。予定通りにすべてをなんの過不足もなく成し遂げること。その事実の大きさに圧倒される。この3月にお会いしたとき、澤本さんはほんのちょっとだが太られたように思った。白髪も増え、おじいさんになった(失礼、でも私も同じだけおじいさんになったんだから仕方ないですね)。今も毎日走り続けておられるという。私は自分がちょっと恥ずかしかった。でも、走ることが人生の一部である人もいるし、そうでない人もいる。走っていたころ、走らない奴をバカだと思っていたことの方がもっと恥ずかしいことだったと今は気づいている。
※澤本和雄『ゆっくりでいいんだよ~がんばれ難病患者日本一周激励マラソン~』はAmazon.comで買うことができます。
●小さな先住者たち
 2週続けて山小屋の建築現場に行った。先週の台風の影響は敷地内のリョウブの枝が折れていた程度だったが、7号がまた上陸しそうだというので若干心配。
2週続けて山小屋の建築現場に行った。先週の台風の影響は敷地内のリョウブの枝が折れていた程度だったが、7号がまた上陸しそうだというので若干心配。
行くたびごとに周辺の野花の様子が変わる。今は木イチゴがきれいだ。先週見たアザミは台風で吹き飛ばされたのか今回はなかった。そのかわり紫の釣り鐘のような形をした花や星形をした白いミヤマカタバミなど新顔がたくさん増えた。
虫も多く、特にたては蝶は開け放たれた山荘の中をたくさん飛びかっていた。エメラルド色に輝く甲羅をもったカメ虫や胴体が短く羽の半分が透けている蝉や小さなしょうじょうバッタ、綿毛を白く輝かせて這う毛虫。目を凝らせば生き生きとした世界が見えてくる。
ところが期待していた鳥はウグイスやカッコウが時折啼く程度であまり聴かれない。
小屋の方は月末の完成に向けて着々と工事が進んでいる。想像どおりだった部分、そうでない部分、人生同様いろいろある。自然の中に分けいっていく私たちはこれ以上彼らの邪魔をしないようにしよう。先住者たちに住まわせてもらうのだから。
●ののの家近況
一番下の「の」であるM乃は今年中学3年。高校までのんびり暮らさせたいと思って上2人と同じ中高一貫の女子校へやったのだが、どうもここが居心地悪いらしく高校は都立へ行きたいと言いだしている。校則のやかましさから逃れるためではないかと私は思っているのだが、そういう理由ならなおさらここで今の学校から離れさせるのはいやなのだが… 最近ふてくされてばかりいて顔がとげとげしくなった。剣道の方は適当に続けており(ほとんど試合に出ても勝てない)、先日2段審査に合格した。
二番目の「の」、Y乃はM乃と同じ学校の高等部2年。ヴァイオリンの腕はランニングで言えば市民ランナーの上位クラスという感じだろうか? 今ブルッフの協奏曲を弾いている。この子がつい先日までエステティシャンというわけのわからない仕事に憧れ、その手の専門学校の案内書ばかり集めていた。ところが夏休み前に急に音大の受験講習会に行きたいと言いだし、私たち夫婦は喜んでいる。それからというものピアノとヴァイオリンの練習に熱が入っている。今、出身小学校のプール指導のバイトをしている。
三番目の「の」A乃は今日二十歳になった。短大の卒論を抱えているのに、ディスカウント酒屋で力仕事のバイトをし、空いている日は友達と遊んでばかりいる。この子はこれまで3回海外で誕生日を迎えるといういい思いをしてきたが、今年は山小屋の完成が間に合わず、山での誕生日は迎えられなかった。この就職難の時代、いい口があったら短大卒で就職しちゃいえばいいのに、来年から保母になるための専門学校へ行くと言っている。お金は自分で出すからと言っているが、携帯を買うときもそう言った。たぶん携帯同様親が出すんだろう。
FERMATAはこれまで夏休みがある数少ない職種の人だったが、今年から夏休みがなくなり、毎日お客さんのいない職場へ出かけていっている。もともとこの職場、何時間時間外に働いても超過勤務手当も代休もでないのだが今後断固として要求すべきだろう。とある大新聞は夏休みがなくなったことについて「長年の溜飲が下りた」と感情論的な論説を書いた。他の職種と足並みを揃えろとヒステリックに叫ぶのなら、当然勤務の実態をきちんと把握してそれなりの報酬を認めるべきである。
私は毎年定員削減で個人がこなさなければならない仕事量が増大している。どこも楽じゃないことはわかっているのだがこのままだといつか壊れる。フリーズして、再起動かけても動かないパソコンみたいになりそうだ。…だから、というのではないが山へ逃げようとしている。週末だけの山暮らしになるけれど自分を取り戻さないと何のための人生だかわからなくなる。とはいうものの、遠く離れた土地に家を建てるなんて初めての経験にも結構ストレスを感じている。薪ストーブの前にごろんとしてなかなか読めなかった本を思い切り読む、なんて図を思い描いて、あれこれの不満や不安を心の隅に追いやってはいるが、始めてみないとどうなるかわからない。
●死と再生の森@ALT1249
週末だけの森の生活がスタートした。涼しいのは標高1249mだから当然なのだが通り雨や夕立があっても湿度計の針が「comfortable」の域から出ないから気持ちいい。
日中は網戸を開けたり玄関を出入りするたびに虻や蝶・蛾が飛び込んでくる。そして夜になると様々な虫たちが明かりを求めて窓辺に集まる。まるで枯れ葉そのままのような蝶、幽かな色合いの透き通った羽の蝶、名前もわからない小さな虫たちが二重ガラスの窓に貼りついたりぶつかったりしている。私たちを歓迎してくれているのか抗議に集まっているのか、いずれにせよ白熱灯の明かりの下で酒を飲んだくれている人間を偵察しにきているようだ。しかし、翌朝窓の桟に折り重なるようにして死んでいるのも彼らだ。網戸越しにふっと吹き飛ばすとぱらぱらと落ちていくたくさんの死骸。おそらく彼らは私の小屋の窓辺を終焉の地にして寿命を迎えただけのことなのだろうがこうして毎日たくさんの虫たちの死に直面すると森がたくさんの死を抱えていることを実感する。目に入らない広大な山のなかでは多くのものたちが行列をなして刻々と死を迎える順番を待っている。
 しかし森はまた再生の地でもある。木漏れ日の下、葉の上で反対向きになって交尾する蝶たち。ベランダの上を這い続けるきれいな色の毛虫やいも虫たち。夜ごとあれだけの死を供給するためにはそれ以上の再生がなされているに違いなく、こうして森は生き生きとしつづけていられるのだ。
しかし森はまた再生の地でもある。木漏れ日の下、葉の上で反対向きになって交尾する蝶たち。ベランダの上を這い続けるきれいな色の毛虫やいも虫たち。夜ごとあれだけの死を供給するためにはそれ以上の再生がなされているに違いなく、こうして森は生き生きとしつづけていられるのだ。
彼らの多くは実に質素でどうということのない姿形をしており、それがまた文字通り自然の natural さを感じさせてくれるのだが、ときとして自然は芸術的な色彩や造形を当たり前のように、実に natural に投げ出してくることもある。ルリボシカミキリはまだ序の口なのだろうが、40数年前から都会っ子だった私には小屋の板壁の上で見つけたこの5cmほどの昆虫は十分すぎるインパクトを与えた。つや消しのマリンブルーにつや消しの黒のドットが鮮やかなおしゃれな虫はカメラのシャッターを切った直後、羽を広げて45度の角度を保って朝の森の中に消えていった。
●秋の気配
 先週末ごろから東京は涼しく夜などは寒いくらい。熱帯夜が続いていたころに出したタオルケットだけで寝ていると朝方は蓑虫のように体を丸めている。もう夏も終わりだと焦っているのかみんみん蝉がいっせいに鳴く。
先週末ごろから東京は涼しく夜などは寒いくらい。熱帯夜が続いていたころに出したタオルケットだけで寝ていると朝方は蓑虫のように体を丸めている。もう夏も終わりだと焦っているのかみんみん蝉がいっせいに鳴く。
もう避暑ムードではなくなっており山では冬の準備をしなくちゃと思っている。敷地から切り出した丸太が山積みになっており、最初はストーヴ用の薪にするつもりだったが、その前に庭の整備をしようと思っている。チェーンソーに大ハンマー、なた、スコップなどを使って、砂利だけが敷いてある駐車スペースから玄関までのアプローチを丸太で補強し、うちの敷地と道路との間ののり面も丸太で補強しておかなければ… 先日造園業をしている知り合いにノウハウを仕込んでもらったが実際自分の手でやってみないことにはどの程度大変かわからない。ここまで全部業者にやってもらった山小屋づくりの仕上げを少しずつ自分なりに手がけていこうと思っている。
●森の新しい仲間と敵
 8月最終週を山で暮らした。薪割りや庭の階段づくりに明け暮れながら森の生活の第一歩を踏み出した。東京では毎日30℃を越える猛暑が続いていたこの一週間、窓辺の温湿度計が示した森の最高気温は25℃を越えなかった。直射日光の当たる庭で杭打ちをしていると汗はかいてくるが手を休めた途端にすうっと引いていく。
8月最終週を山で暮らした。薪割りや庭の階段づくりに明け暮れながら森の生活の第一歩を踏み出した。東京では毎日30℃を越える猛暑が続いていたこの一週間、窓辺の温湿度計が示した森の最高気温は25℃を越えなかった。直射日光の当たる庭で杭打ちをしていると汗はかいてくるが手を休めた途端にすうっと引いていく。
1月以降この森に入るたびに感じた自然の変化は今回も新しい姿を見せた。昼夜を問わず飛び回る虫の数が減った。トンボが増えた。花も顔ぶれが変わった。小さな目立たない花が増えた。萩の淡い花があちこちに咲いていたが初夏の山ツツジ同様実に控えめな花だ。色彩の少ない森の中で赤く色づきはじめたナナカマドが目に飛び込んでくるくらい。そんな秋の装いを刻々と進める森の木立の間から小さな蝶が舞い降りてきた。ルリタテハ… 当たり前だが図鑑に出ているとおりの色と姿をしている。ヒョウモンタテハは数多く飛来していたがルリタテハに会ったのは今回が初めて。デッキの上に黒い影を映しながら素早く飛びまわる姿は静止画に収めきれないこの蝶の魅力だ。3日連続午前10時過ぎに現れたがその後見なくなったのは生涯の仕事を終えたからなのか、別天地を見つけたからなのかわからない。
 パートタイムの山暮らしをしてみて新しい問題にぶつかった。何もかも人任せの暮らししか知らない都会人の出会った最初の敵は剥き出したすねを刺すアブやぶよの類ではなく、実は自分たちの出すゴミだった。リサイクルできるゴミはすべて分別整理して村に一つしかないスーパーマーケットか隣町の大型マーケットに備え付けられたボックスに戻す。紙類はなど燃やせるゴミは焼却炉を作って燃やす。燃やすことのできないゴミはなるべく出さないような買い物をし、出てしまったら東京に持って帰る。最後に生ゴミが残ってしまった。前回のショートステイの時も小袋一つ分くらいの生ゴミが出、処理に困って庭の隅に穴を掘って埋めた。ところが危惧していたとおり今回着いてみると掘り返されていた。たぶん狸か何か小動物の仕事だろうが、彼らのせいではない。今回のように一週間以上の滞在になるとたとえそれがタマネギ、人参などの野菜や果物の調理時に出るゴミだけでも結構な量になる。魚や肉類は同伴したパウ(犬)とトラ(猫)が最終的に処理してくれるので出さないで済んだが、どうしても植物系のゴミが残った。コンポストを買ってきて放り込んでしまうという方法に挫折している人の話はたくさん聞いていたので別の方法を模索していたが簡単には始められず、結局今回は高い金を出して管理事務所からゴミ袋を買い、処理を依頼した。自分たちの敵は自分たちだった…
パートタイムの山暮らしをしてみて新しい問題にぶつかった。何もかも人任せの暮らししか知らない都会人の出会った最初の敵は剥き出したすねを刺すアブやぶよの類ではなく、実は自分たちの出すゴミだった。リサイクルできるゴミはすべて分別整理して村に一つしかないスーパーマーケットか隣町の大型マーケットに備え付けられたボックスに戻す。紙類はなど燃やせるゴミは焼却炉を作って燃やす。燃やすことのできないゴミはなるべく出さないような買い物をし、出てしまったら東京に持って帰る。最後に生ゴミが残ってしまった。前回のショートステイの時も小袋一つ分くらいの生ゴミが出、処理に困って庭の隅に穴を掘って埋めた。ところが危惧していたとおり今回着いてみると掘り返されていた。たぶん狸か何か小動物の仕事だろうが、彼らのせいではない。今回のように一週間以上の滞在になるとたとえそれがタマネギ、人参などの野菜や果物の調理時に出るゴミだけでも結構な量になる。魚や肉類は同伴したパウ(犬)とトラ(猫)が最終的に処理してくれるので出さないで済んだが、どうしても植物系のゴミが残った。コンポストを買ってきて放り込んでしまうという方法に挫折している人の話はたくさん聞いていたので別の方法を模索していたが簡単には始められず、結局今回は高い金を出して管理事務所からゴミ袋を買い、処理を依頼した。自分たちの敵は自分たちだった…
しかし、毎回人に頼ってばかりいたのでは町中で暮らすのと何も変わりはなくなってしまう。今大急ぎで勉強中なのはミミズのこと。ミミズたちの住まいをどうするか、夏はともかく冬も有効かどうか、しばらく行かない間のミミズの食料のことなど、どうしてよいかわからない問題も多いのだが、これまで無視どころか毛嫌いしていた彼らに十分詫びを入れて世話になってみるのも悪くないと思っている。
●家族増員計画
 秋らしい秋を通り越して夏から一気に晩秋の気候になり風邪をひいてしまった。山小屋がある村のピンポイント天気情報によれば今日の最高気温は21℃、村のどこを標準にしているのかわからないのだが小屋のある標高1249m辺りはさらに1~2℃は確実に低い。この調子でいくとストーブに薪をくべる機会はかなり早くやってきそうだ。
秋らしい秋を通り越して夏から一気に晩秋の気候になり風邪をひいてしまった。山小屋がある村のピンポイント天気情報によれば今日の最高気温は21℃、村のどこを標準にしているのかわからないのだが小屋のある標高1249m辺りはさらに1~2℃は確実に低い。この調子でいくとストーブに薪をくべる機会はかなり早くやってきそうだ。
仕事で東京を離れられなかった9月最初の3連休、暇さえあればミミズのことばかり考えて過ごしていた。ミミズを使って生ゴミの処理を行っている人や団体のサイトをほとんど回り、マニュアル本(『生ゴミを食べてもらうミミズ御殿の作り方~ミミズコンポスト完全マニュアル~』)も買って読んだ。実際に自分で始めないかぎりうまくいくかどうかはまったくわからないが、少なくとも生ゴミをポイと容器に捨てるとミミズが勝手に処理をしてくれるといった夢のような話ではないことだけはわかった。と同時に人間が自分たちの出すゴミに埋もれ始めているのはゴミを容易に捨てられない山暮らしであるかどうかとは関係なく、地球上どこでも同じだということもわかった。数年前、生ゴミ等を処理している区の焼却場に行ったことがある。悪臭と熱気に包まれながら大変なお仕事だなあと思ったがそれ以上に自分の視野を広げて考えることはなかった。自分を取り巻く日常の中から自分にとって優先度が高いと思いこんだ事柄を並べて作られた to do リストにゴミの問題は入ってこなかった。産業廃棄物というとその言葉自体が発散する「悪役」の気配が立ちこめてくるけれど、家庭ゴミというと小さなゴミ袋にこぢんまりと収まった生活の残滓にすぎないという自己暗示がかかってしまう。ところが次々とやってくるゴミ収集車が落としていく家庭ゴミの山はそれを出したそれぞれの人間との関係を切断され、出してよいゴミもいけないゴミも一緒くたになって高温で焼かれ、大気を汚染し周辺の土壌を汚染していくのだ。今さらながら自分を含めた人間のエゴが万物を乗せた地球丸を沈没させようとしているのだと気づいた。
そこでミミズを使ってゴミ処理をするという一つの方向が再認識され、その運動が静かに進行している。私自身もゴミを処理してもらうという意図でこの問題を見つめだしたのだが、実をいうと今の心境は当初の意図とは微妙にずれてきているのを感じる。私たち人間とその子孫が暮らしていくこの地球をすべての生物と正常な関係を保ちつつ守っていきたいという大義は消しようもないことなのだが、実はそれとは違う別の興味に今心がひかれているのだ。それもまた人間の驕ったエゴなのかもしれないが、私はミミズを飼ってみたいのだ。ゴミ処理をする道具としてではなく、うちの犬や猫たちが私の家族であるようにミミズを家族の一員として生活してみたいのだ。ミミズのためによい環境を作り、彼らの好む餌を与え、彼らとともに一喜一憂したいのだ。3連休の最後の今日、まずミミズ御殿の第一号を作ろうと思っている。→ミミズとの生活の逐一は掲示板で進めていく予定です。
●やっと会えた先住者
 ついこの間までたくさんいた虫たちの姿もすっかり目にしなくなり森は静かに冬へ向かっている。日中でもデッキに素足で出ると思わずぞくっと身震いしてしまう。標高が高いせいでもともと草花がふんだんにあるという場所ではないのだが、めっきり花の数も減った。本格的な冬に入ったらとんでもなく寂しくなりそうな、そんな気がする。
ついこの間までたくさんいた虫たちの姿もすっかり目にしなくなり森は静かに冬へ向かっている。日中でもデッキに素足で出ると思わずぞくっと身震いしてしまう。標高が高いせいでもともと草花がふんだんにあるという場所ではないのだが、めっきり花の数も減った。本格的な冬に入ったらとんでもなく寂しくなりそうな、そんな気がする。
デッキに灯していたスポットライトの明かりに誘われた大きな蛾の群が山小屋の壁に貼りついているだけで寂しさが紛らわされるほど生き物の気配がしないのだ。たとえばこんな森の奥にひとり1週間こもっていたら落ちついて本など読んでいられるのだろうか。都会の喧噪の中にいれば静寂を求めるくせに、実のところ本物の静寂の中に放り込まれたらいてもたってもいられなくなりそうな不安を感じるわがままな自分を発見する。
雨が降り出した。一段と寒さが増してくる。白熱灯の発散する熱がほのかに伝わって温かい。昼だというのに灯りを煌々とつけて熱いコーヒーをすする。
こういう生活がほんとうにしたかったのか? たぶん… 昨夜来ていた友人一家が朝早くに帰ってしまったらから… 帰りたくなさそうにロッキングチェアで丸まっていた友人の子どもたちの姿が焼きついてしまって心が不安定になっているだけ…
 下界へ買い物に行こう。
下界へ買い物に行こう。
急な山道を車で下っていく。 ローレンジにギヤを入れても車はどんどんスピードを増していく。大きなカーブをドリフト気味に曲がった途端、黒いつぶらな目がじっと私を見つめた。私はあわててブレーキを踏んだ。体長1mほどの子鹿がすっくと首を伸ばし、こちらを見ていた。体にはまだ黒の斑点がありバンビそのものだ。親鹿は視界にいなかったが、近くにいただろう。と、次の瞬間、子鹿は華奢な体を翻すと谷になっている森の中へ消えた。
こういう生活がほんとうにしたかったのか?
まだまだ知らない森の生活がここにはある…
●最近のできごと
![]() 番目のご来訪者からメールで証拠画像が送られてきた。ここまで何年かかったろうか。毎日小銭を稼ぐようにせこせことカウンタを重ねてきたが継続は力なり。当分はやめずに戯言を続けていくつもりなのでリピーターのみなさんよろしくおつきあいください。
番目のご来訪者からメールで証拠画像が送られてきた。ここまで何年かかったろうか。毎日小銭を稼ぐようにせこせことカウンタを重ねてきたが継続は力なり。当分はやめずに戯言を続けていくつもりなのでリピーターのみなさんよろしくおつきあいください。
 先週山小屋に念願のピアノを入れた。たいして弾く機会がないのにもったいないとも思ったのだがのののたちが自分たちの貯金をはたいて買うというので踏み切った。家にあるピアノよりも遙かにいいピアノで、弾けない私が音を出しても違いがわかる。プルツナー(ドイツのブリュツナーではない)という無名のピアノなのだが作りも音も国内量産メーカーの同クラスよりずっとよかった。最初の頃は私たち親が貯めてやり、途中から自分たちのお年玉を貯め続けた彼女たちの貯金が1台の、頑固者の職人が作ったピアノに変わった。クレーンでつり上げられたピアノが木梢の間を縫って天から舞い降りてきた。深い低音の響き、粒の揃った高音の艶やかさが物の少ない広い空間に響く。娘の弾くゴールドベルクを聴きながら飲む酒はまたうまい。まさに天からの贈り物…
先週山小屋に念願のピアノを入れた。たいして弾く機会がないのにもったいないとも思ったのだがのののたちが自分たちの貯金をはたいて買うというので踏み切った。家にあるピアノよりも遙かにいいピアノで、弾けない私が音を出しても違いがわかる。プルツナー(ドイツのブリュツナーではない)という無名のピアノなのだが作りも音も国内量産メーカーの同クラスよりずっとよかった。最初の頃は私たち親が貯めてやり、途中から自分たちのお年玉を貯め続けた彼女たちの貯金が1台の、頑固者の職人が作ったピアノに変わった。クレーンでつり上げられたピアノが木梢の間を縫って天から舞い降りてきた。深い低音の響き、粒の揃った高音の艶やかさが物の少ない広い空間に響く。娘の弾くゴールドベルクを聴きながら飲む酒はまたうまい。まさに天からの贈り物…
今回はさほど寒くなったが寒くならないうちに試運転をしておこうと薪ストーヴに火を入れた。着火自体はうまくいくのだがなかなかストーヴ本体が暖まらず煌々と燃えるという感じにはならなかった。でもかなり感触はつかんだのでもう大丈夫。次は水道の水抜き作業をマスターしなくては。
●黒板五郎の流儀
自転車のタイヤを交換した。M乃の通学用自転車で、いわゆるママチャリというやつ。何度パンクの修理をしてもすぐまたパンクするので前からタイヤがもうダメなのだろうと思っていたのだが、空気を入れてみると案の定タイヤの裂け目からシュウシュウ音がしていて、もうタイヤ内部の繊維が飛び出すくらいになっていた。何せロードレーサーのタイヤなら外したことはあるが、ママチャリの後輪はブレーキやチェーンの他にもスタンドや荷台などがくっついているので外しにくい。
自転車屋が近いので持っていけば何てコトはないのだが、ホームセンターも近く、そこには幾らもしないでタイヤやチューブが売られているのも知っていた。ここはお金の問題よりもポリシーとして自分で直したかった。それが五郎さんの流儀なのだ。もっとも五郎さんなら廃品の中から使えそうなタイヤとチューブを見つけだしてくるにちがいないのだけど。
 山には先週3週間ぶりに出かけた。あたり一面黄色に色づいて落ちてきた松葉が敷き積もって醜かった工事跡の黒土も消えていた。
山には先週3週間ぶりに出かけた。あたり一面黄色に色づいて落ちてきた松葉が敷き積もって醜かった工事跡の黒土も消えていた。
2日の朝6時に目を覚まして居間のカーテンを開けると、デッキも屋根も白くなっている。霜かと思ったら、たぶん夜の間にさっと降った雪だった。氷点下なので降ってきたときの粒々のままに凍り付いていた。
日が昇り始めると、葉を落とした木々を通して部屋の窓から富士のシルエットがくっきり見えた。
 温度計をストーブトップにはりつけて本格的に燃やしてみた。焚きつけはすぐに慣れたが、火が安定してストーブ本体の温度が150℃を越すのに2時間以上かかった。そのときの室温は12~15℃。ボタン一つで瞬時に暖がとれて当たり前の生活、「寒くない」を通り過ぎて暑いくらいでないと暖まった気がしない生活、そういう生活に慣れてしまっているから辛いと言えば辛いのだが今は自分が選択した自然の中の生活だからそれが楽しくもある。時間にしても、暖にしても、情報にしても全てが都会流の生活を離れ、五郎流に生きるということの真似ごとをしている。今はまだ自分を見つめる余裕もなくあたふたしていることが多いのだけれど。
温度計をストーブトップにはりつけて本格的に燃やしてみた。焚きつけはすぐに慣れたが、火が安定してストーブ本体の温度が150℃を越すのに2時間以上かかった。そのときの室温は12~15℃。ボタン一つで瞬時に暖がとれて当たり前の生活、「寒くない」を通り過ぎて暑いくらいでないと暖まった気がしない生活、そういう生活に慣れてしまっているから辛いと言えば辛いのだが今は自分が選択した自然の中の生活だからそれが楽しくもある。時間にしても、暖にしても、情報にしても全てが都会流の生活を離れ、五郎流に生きるということの真似ごとをしている。今はまだ自分を見つめる余裕もなくあたふたしていることが多いのだけれど。
●薪の確保と薪割り術
 山小屋完成時に施工してくれた会社からもらったすぐに使える乾いた薪5束はあっという間に使いつくし、夏の間に作っておいた生乾きの薪にも手を出してしまい、仕方なく最寄りのホームセンターで薪を買う。1束580円を1泊2日で3束使う。この冬はもう間に合わないので軽トラ1台分くらいをまとめて買ってしまうしかないだろう。売っている薪はナラか栗の堅薪でよく乾いているからとってもいいのだが《黒板五郎流》ではない。やっぱり自分で切って割って丹精込めて乾かした薪を使いたい。山道を歩きながら倒木が落ちていたりすると引きずってきて切ってみるのだが下草に埋もれるようにして朽ちかけた倒木はもうすかすかで薪にならない。薪を燃やすといっても固体の木そのものが燃えるのではなく熱せられた木が吹き出す可燃性のガス(気体)が燃えるので朽ちてしまったた木は燃えないのだ。木の中の水分がとんで木質エキスがたっぷり残った頃合いの薪を作ること。それがもっかの課題なのだが材料にする木をどう確保するかがその前の問題なのだった。
山小屋完成時に施工してくれた会社からもらったすぐに使える乾いた薪5束はあっという間に使いつくし、夏の間に作っておいた生乾きの薪にも手を出してしまい、仕方なく最寄りのホームセンターで薪を買う。1束580円を1泊2日で3束使う。この冬はもう間に合わないので軽トラ1台分くらいをまとめて買ってしまうしかないだろう。売っている薪はナラか栗の堅薪でよく乾いているからとってもいいのだが《黒板五郎流》ではない。やっぱり自分で切って割って丹精込めて乾かした薪を使いたい。山道を歩きながら倒木が落ちていたりすると引きずってきて切ってみるのだが下草に埋もれるようにして朽ちかけた倒木はもうすかすかで薪にならない。薪を燃やすといっても固体の木そのものが燃えるのではなく熱せられた木が吹き出す可燃性のガス(気体)が燃えるので朽ちてしまったた木は燃えないのだ。木の中の水分がとんで木質エキスがたっぷり残った頃合いの薪を作ること。それがもっかの課題なのだが材料にする木をどう確保するかがその前の問題なのだった。
と見るとうちのすぐ下の山から切り出されたナラの木の丸太が小道の脇に放り出されている。こっそり持ってきてしまうわけにはいかないけれど不要のものなら欲しいと思っていたら木の植え替えをしていた職人さんがやってきた。話を聞くと始末しようと思っていたところだから持っていくなら持っていっていいよと言う。さっそくFERMATAと二人でうちの敷地まで運び始めたがどうしても数本動かすことすらできない太い丸太が残ってしまった。これは私たち二人が必死になって動かそうとしているところを見かねた職人さんがショベルカーで運んでくれた。
 1週間後、細い(15cmくらい)丸太をチェーンソーで玉切りにし、太めのものは斧で割った。立てた丸太の芯の手前側に斧を落としてその衝撃でパカーンと割るのがコツだ。包丁を入れるみたいに斧の刃で切るわけでないのだ。素性のいい木は当てどころさえ狂わなければ山にこだまするくらいのよい音をたてて二つになる。幼いころからいじめられてきた木は容易には割れないが何度か斧を叩き込んでいるうちに節の部分を迂回して割れる。斧を当てる部分からけっして目を離さずに、十分に高く振り上げ、力を入れずに振り下ろし、当たる瞬間に手の内を締める。真芯に当たるとボンズ級の場外ホームランだなと感じる。ほんのわずかでも中央より向こう側に当たると鈍い音がして凡フライになる。ここ数年来の座骨神経痛をおして頑張るが、自分たちで庭まで運べなかった太い丸太にまでは手が回らなかった。お楽しみはまだつづく…
1週間後、細い(15cmくらい)丸太をチェーンソーで玉切りにし、太めのものは斧で割った。立てた丸太の芯の手前側に斧を落としてその衝撃でパカーンと割るのがコツだ。包丁を入れるみたいに斧の刃で切るわけでないのだ。素性のいい木は当てどころさえ狂わなければ山にこだまするくらいのよい音をたてて二つになる。幼いころからいじめられてきた木は容易には割れないが何度か斧を叩き込んでいるうちに節の部分を迂回して割れる。斧を当てる部分からけっして目を離さずに、十分に高く振り上げ、力を入れずに振り下ろし、当たる瞬間に手の内を締める。真芯に当たるとボンズ級の場外ホームランだなと感じる。ほんのわずかでも中央より向こう側に当たると鈍い音がして凡フライになる。ここ数年来の座骨神経痛をおして頑張るが、自分たちで庭まで運べなかった太い丸太にまでは手が回らなかった。お楽しみはまだつづく…
●薪割り術(その2)
 3週間前に残してきた丸太を薪にしようとFERMATA(とPAU)とで山に出かけた。前回薪にしたのは最高でも20cmくらいまでの丸太だったが今回の丸太は30~35cmと太い丸太。薪割りの秘訣の一つに丸太の中心より手前に斧を落とすと前回書いたが実は直径が35cmもあるとこの手は通用しなかった。どこを叩いてもはじき返されるだけで立ちすくんでしまった。手前なんか叩いたってちょこっと傷がつくだけで埒があかない。しかしチェーンソーで40cmくらいの長さに玉切りにした丸太は20個以上もあり、そのままにしておくとまるで7人の小人の椅子みたいでどうしようもない。こうなったら気力で割れるまで叩き続けるしかない。そして試行錯誤を続けた結果、太いやつは手前ではなく中心より向こう側に斧を目一杯叩きつけ続ける方が効果的であることがわかった。最初は手がしびれるほど簡単に跳ね返されるが我慢して5回くらい同じ辺りを叩き続けると音が鈍くなり縦に亀裂が入り始める。こうなればパコンと割れるのは時間の問題だ。途中で立ちくらみがし、左の掌に出来たマメがつぶれた。革手袋をはめて握っている斧の柄が滑り出し放してしまいそうになる。日の出直前に起き、朝食前に始め2時間格闘を続け全てを割り終えた。木に与えた衝撃と同じ量の衝撃を添えていただけの右手が集中的に受け打撲症状が出ている。
3週間前に残してきた丸太を薪にしようとFERMATA(とPAU)とで山に出かけた。前回薪にしたのは最高でも20cmくらいまでの丸太だったが今回の丸太は30~35cmと太い丸太。薪割りの秘訣の一つに丸太の中心より手前に斧を落とすと前回書いたが実は直径が35cmもあるとこの手は通用しなかった。どこを叩いてもはじき返されるだけで立ちすくんでしまった。手前なんか叩いたってちょこっと傷がつくだけで埒があかない。しかしチェーンソーで40cmくらいの長さに玉切りにした丸太は20個以上もあり、そのままにしておくとまるで7人の小人の椅子みたいでどうしようもない。こうなったら気力で割れるまで叩き続けるしかない。そして試行錯誤を続けた結果、太いやつは手前ではなく中心より向こう側に斧を目一杯叩きつけ続ける方が効果的であることがわかった。最初は手がしびれるほど簡単に跳ね返されるが我慢して5回くらい同じ辺りを叩き続けると音が鈍くなり縦に亀裂が入り始める。こうなればパコンと割れるのは時間の問題だ。途中で立ちくらみがし、左の掌に出来たマメがつぶれた。革手袋をはめて握っている斧の柄が滑り出し放してしまいそうになる。日の出直前に起き、朝食前に始め2時間格闘を続け全てを割り終えた。木に与えた衝撃と同じ量の衝撃を添えていただけの右手が集中的に受け打撲症状が出ている。
●「第9」
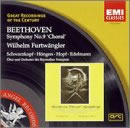 掲示板で小澤&サイトウキネンの「第9」をこき下ろしてしまってから気になっていた。小澤征爾という人物は嫌いじゃないし、むしろその生き方は好きなのだが彼の演奏を聴いて感動しないことも確かで、だからこそ素面なのにあんなことを書いてしまったのだ。でもちゃんと聴きもせずに簡単に決めつけたようなことを書くべきでないと反省し腰を据えて聴いた。結論はもはや書かないことにする。
掲示板で小澤&サイトウキネンの「第9」をこき下ろしてしまってから気になっていた。小澤征爾という人物は嫌いじゃないし、むしろその生き方は好きなのだが彼の演奏を聴いて感動しないことも確かで、だからこそ素面なのにあんなことを書いてしまったのだ。でもちゃんと聴きもせずに簡単に決めつけたようなことを書くべきでないと反省し腰を据えて聴いた。結論はもはや書かないことにする。
そうして辿り着いたのはやっぱりフルトヴェングラーの51年バイロイト盤だった。じっとして聴いていられない、腰が浮いて、脈拍が増え、全身に鳥肌を立つ感覚はちょうどジェットコースターに乗ってアプローチを上りつめたときの感じだ。素人だから専門的なことはわからないのだが、どの音符も一つ一つそれぞれの質量を持ち、50年の時を経てなお、今生まれたばかりのようにぷるぷると震えて脈動している。それが巨大な生成真っ最中の宇宙を構成している。同じことは42年、47年の第5《運命》にも言えるのだ。モノラルの、それはもう今の録音と比べたらとんでもない音源なのだが、これがベートーヴェンなのだと納得させられるのに不足はない歴史的な名盤なのだ。
●擬似遭難体験
 9~10日の雪は東京でもわが家の辺りでは10cm以上積もったが山では25cmだったらしい。今回の連休は前日の20日から山は雪の予報だった。それも前回を上回るとピンポイント情報をつかんでいた。
9~10日の雪は東京でもわが家の辺りでは10cm以上積もったが山では25cmだったらしい。今回の連休は前日の20日から山は雪の予報だった。それも前回を上回るとピンポイント情報をつかんでいた。
家を出発したのは21日午後2時前、車のウィンドウにあたる水滴は中央道に乗る前にはみぞれになり始めていた。上野原・勝沼間チェーン規制の電光掲示。普通ならここでやめておくはずなのだが、チェーン規制というのがどういうものか、そういう状態で走行するというのがどういうことか、こんな状態のとき山はどうなっているのか知りたかった。つまり、全て未体験のことだった。
雪の中に埋もれた山小屋に着いたのは午後11時になろうとしていた。その間のことはまったくとてつもない経験だった。結局車は山小屋のずっと下に置いて登った。立ち往生というのが正しい。実は最後の段階で雪道にはまり、動けなくなった。チェーンが飛んで動けなくなったため、再度チェーンを付け直すのに小一時間かかった。雪かきから始まり、深い雪の中でジャッキアップしてようやくチェーンを装着し直し、雪だまりから車を出して道の脇に寄せるためだけにだ。
そこから荷物を担いでPAUの先導で山道を登った。深夜なのに雪明かりで森の中は明るかった。鹿の親子三頭と出会った。とんでもない半日だった。けれども、わくわくしていた。50近くになって初めて経験する雪だけの世界。PAUと私の息づかいしか聞こえない静寂の中で時折「ばきーんー」と雪の重みで木が折れ、雪とともにどさっと落ちる音がした。その度にPAUと一緒にドキッとして周囲を見回した。地響きとともに「ぐぉおおー」と雪崩の音もした。とにかく数百m先のわが家に早く入ってほっとしたい、そう思いながら急坂を上っていった。
A乃とM乃は帰ればよかったとぶうたれながら後からやってきた(Y乃はヴァイオリンのレッスンで来なかった)。屋根から落ちた雪だまりで、小屋の周りは腰近くまで雪があった。通水作業をしてストーヴに火を入れる。緊張感で8時間半に及ぶ運転も辛く感じなかったのに、部屋が暖まり出すともう起きてはおられなかった。